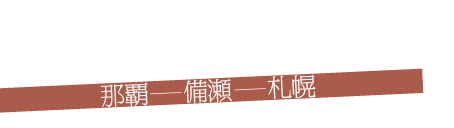12
那覇で最後の琉球舞踊講習を終え、おもろまちの沖縄県立博物館・美術館から壷川にある宿泊施設までPoさんと2人で移動することとなった。
Poさんは広東語はもちろん、英語もできるためにWei師傅と日本人サイドとの通訳をも兼ねている。そのために彼のことを身近に感じていたところもあったのだが、いざ二人になってみると、英語力が中学生を下回る私との間では案外話をするのが難しいことに気が付いた。これは、私とWei師匠との間でスマホ・アプリを駆使して話をするようになってからも、どこかこの間接的な対話法がPoさんとの間ではかどらなかったことと地続きの事柄であったように今となっては思う。ひとたびこのような迂遠さを感じると、コミュニケーションというのはなんとはなしに滞りを見せたりするものだが、元来の落ち着きのなさが彼らの気さくさに救われ、私は彼らとふざけるという回路だけは断たずにすんだし、その回路がそのほかの話に関しても道を開いてくれていたように思われる。
今回のクリエイションを進める上で、Poさんには、作品作りにこだわらずともドキュメントを提示する形でも成果として発表できるはずであるというような意見などを私は提案していた。Poさんからは通訳の川口さんを通して「私もそう思う」というような反応であったと思う。こうしたクリエイションとその成果発表に関する話には、時折私の想定と同様の意見が彼からも聞かれたこともあり、合意形成話をとるうえでは話がはやそうだと思ったりした。とはいえ、そうした意見は言うものの、ダンスに関するクリエイションをしていくうえで、ナマズのようにどろ~んとした私の舞台上での使いみちには苦慮したのであろう。伝統の枠組みに制限されることはあるがこれまでも共に仕事をし、体の利くWei師匠とは異なり、悩みの種として彼らは私とこのクリエイションで何かしらのコミュニケーション、そしてその先に必然化するシーンの構想を練らなくてはならなかった。また、私をシーンとシーンをつなぐ解説役にするなどの具体策も上がりはしたが、私の口調がもつニュアンスについて判断ができない彼らにとっては、プロデューサー・水野さんの最後のまくし立てを待つほか採用に至る動機がなかったのである。言葉運びにはそれぞれニュアンスがあるものだが、それが示す性格などを加味したうえでこれがどのような効果を示すかを想定・判断することは非常に難しい。まして彼はダンス作品の構成者であり、それに輪をかけて私とは言語が異なるのである。
私はそれぞれの沖縄の滞在経験やこれまでのコミュニケーションの中からシーンが自然と浮かび上がってくるその必然性を待つ体で、ぼんやりと彼らとの時間を楽しもうとしていた。
Poさんもまた、シーンの必然性を共に過ごす中から見極めざるを得ないと思いつつ、同時にWei師匠と進め方に関する意見の相違の中で合致点を探ってもいたようである。
Wei師匠にはすでに舞台作品を成型する上での型が備わっている。その型をシーンごとの情景描写における必然性と突き合わせていくことでおそらく無数にシーンとしてのバリエーションを構成できるはずなのである。ただし、この方法が演劇よりの制作ならともかく、ダンスに関する制作作業にとって有効に働くかはちょっとわからないところがあった。であるから、舞台作品を構成する考え方そのものがすでにPoさんとは異なっていたはずなのである。「はずなのである」というのは、札幌での上演後に彼らが舞台作品を創作するチームを組んでいたことが改めて確認されたからである。二人組で参加している時点でグループであることが分かりそうだが、彼らとともに過ごすなかで、彼らがグループであるということが感じられないくらいに、それぞれ独立した4人でのクリエイションが展開していたあかしでもあるだろう。
ともかくも、そういう伝統に裏打ちされた技術をWei師匠は持ち合わせていたはずだ。この技術や作品作りのノウハウと、Poさんや緒方さんの作品作りのあり方がダンスをめぐるクリエイションとしていかに展開可能かを探ることが、何よりも今回Wei師匠が考える伝統ある京劇の自我同一性を尊重しつつ同時代の舞台芸術に関する創作プログラムに対応した一例として、このプロジェクトと彼の仕事を位置づけることになったことだろう。
しかし、こうして数文字連ねることほどには簡単なことではないのが生身の人間同士の作業である。今回のプロジェクトに彼らが何を思ったのか。今後何かしらのステップへと踏み出す上で彼らのその思いが参照されたとき、初めて中国オペラと同時代的試みのあり方に関するこのプロジェクトの位置づけがより明確化していくことだろう、としか今はまだ言えないところがあるように思う。
Poさんも私も、お互いこの那覇滞在最後の日を一区切りとして、どこか疲れも出ていたのだろう。タクシーの中は、外の渋滞に重なるような倦怠感がにじむようであった。ふと、Poさんが毎日奥さんから送られてくる我が子の映像に相好を崩しているのを見て、彼はもしやホームシックになってはいまいかと、うっすら心配したものだが、それは佳きパパとしての彼が屈託なく姿を見せていただけのことであった。
一方で、同じ2歳の子供があるWei師匠が、子供の映像を見ている状況を人に見せていないことが気になりもしたのだが、それもとりこし苦労といったようなもので、これも二人の性格の違いの表れでしかなかった。師匠は仕事の場とプライベートの場をきっちり区別するタイプのようである。翌日。備瀬に移動した晩、私は背骨と肋骨の間をほぐすマッサージに恐れおののいた後、たっぷりと師匠の愛児の姿を見せてもらった。その時、彼もまた屈託ない笑顔で父親の顔を私に見せてくれたものである。
さて、夕方の渋滞にうんざりし、Poさんとエレベーターで分かれて一人部屋に帰ると、カツオ汁とみそ汁の差し入れがドアノブにかかっていた。私にこんな親切をしてくださる心の美しい方はいったい誰であろうか・・・と、そう思っているところへ、どこかへ食事に行ったとばかり思っていた川口さんから連絡が入った。ドアノブの差し入れは彼女の気遣いであった。この夜は一週間我々の間で通訳をしてくださった彼女の沖縄最後の夜である。すでに二人共に食前酒を召し上がっているとのことで、緒方氏の部屋へと川口さんの労をねぎらい、また緒方氏に洗濯機を借りるために階違いの部屋に向かった。そこへ書類を届けに来てくださった小百合先生も合流し、しばし歓談。入れ替わるように夕食を食べそびれた水野さんもこの部屋へ。「レモンさん、大丈夫なの?昼間のあれは仮病?」と、微熱を残しながらも日暮れとともに落ち着いた私の傷口を、なおも丁寧に消毒するようにして優しく気遣ってくださる水野ねえさんであったが、ねえさんもまた、激務に追われて舌痛症を発症するほどなのであった。愛の深い人である。
なお、私が舌痛症を発したのは、札幌に着くか着かないかの頃であったように思う。
remon