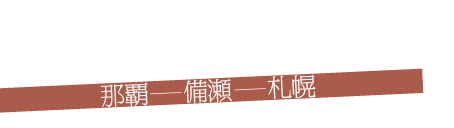11
この講習で学んだ≪マミドーマ≫は、掛け声である「サッサー」とともにすんなりと現代人の労働に関する身振りに置換可能であった。農耕作業の身振りを基に構成された踊り曲である。
鍬や鎌などを持ち、その手と足を同方向へと払う「あしてぃ」という身振りは、片手で持ったスマホをもう一方の指先でスクロールする現在的な振りにとすぐに変容した。小百合先生がくりっとした目を輝かせて微笑んでいる。
一種の転換あそびは「もどき」の形をとって、振りそのものに別の意味を持ち込む形をとることでおかしみを生み出す。Po氏が見せたこの初期段階には、やはりそうした機知の溌剌さがあった。その後のクリエイション過程で、労働を歌と踊りを介してはつらつとした楽しみにと昇華して見せようとしたその大本の意味合いに変容がもたらされた。Po氏はどこか未来あるいは幸福へつながると信じながら行われる行為として労働をとらえつつ、その希望を託し続ける様を種蒔きの身振りに担保する形で、一種の悲哀をもって現代の労働を見つめる方向にと進んだのである。彼自身は明るい男ではあるのだが、まじめさというのは時折暗さをも伴って印象付けられるものである。なにより笑って踏み出す嗚呼の技にと私はかけたいところではあるが。
この振りはこの後、シーンとして採用する上での必然性やその展開の可能性に迷いながらも、Po氏と緒方氏とのデュオ≪ワークソング≫の中に残った。
こうした学習経験をどのようにその後の制作の上に反映させられるのかということもまた、なかなか難しい問題である。少なくともいえるであろうことは、見聞したことをいかに主題化していけるか、あるいはそれがない場合にはいかにその影響を自然な形でシーンの要素にしていけるかということであろうか。面白かったのは「too much」という言葉を後々シーン推敲段階でPo氏も緒方氏も、大まかに「忌避すべき(もの)」の意味として口にしていた点である。そこには前提条件として「ありきたり」などの形容が前置されたりした様子である。
まぁ、その言葉だけでは別にどうということもないだろう。とはいえ案外この「too much」と見たところがPo氏と緒方氏や私などの間で共通しているようにも思われた。それは現代の舞踊シーンにおける共通の感覚をどうやら我々は有していることを証明するものとも思われ、その先の創作段階で話し合えることについてもやや期待が持たれた。とはいえ「too much」みたいな短いセンテンスからいったいどのくらいのことが読みとれるのか、という疑問もないわけではない。
Po氏に対してのスマートな印象は、話の中でのこうしたごく細かい単語の使用傾向などからうかがわれるように思われた。しかし、こういった印象を受けながらも、それでも共同制作上の共有概念を構築する以前に横たわっているコミュニケーションそのものにと目を向けなくてはならなかったのが今回のクリエイションの特徴となった。現代っ子の間での共通感覚だけでは越えられない文化の壁とでもいうべきものがそれぞれにはあったのである。
今回のドキュメントでこうしたことを私がどれだけお話しできるか。そしてどれだけ筆を滑らせることができるか。翻って、そこまで話したらこうしたクリエイション・ドキュメントの「too much」に一応の輪郭を与えることができるだろうか、というのもあるな。まぁ、そんな余計なことも思い付きで話してしまうような具合で、話の流れいかんで思いめぐらせてみることがあるかもしれないし、ないかもしれないなと思うのである。
remon