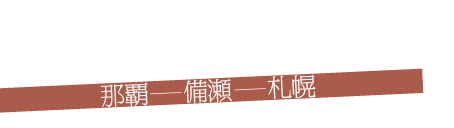14
これから向かう海でどのような生物と出くわすかということの予習もかねて、美ら海水族館へ立ち寄った。
夢中になっていろいろの水生生物をみているといつしか皆とはぐれてしまっていた。必然的に海が喧伝される沖縄の淡水魚も、こうして改めて見る機会がなかったのでとても興味深かい。あれは鮒の仲間にあたるのであろうか、鱗が銀メッキしたようにきらめいたものがあるかと思えば、その科ではどうやら最大級のハゼがいる。危険な海洋生物を見て、またその対処法を確認してのち、大きな水槽のある空間へ出た。回遊するジンベイザメやエイの姿にくらくらしそうになる。サメの水槽もいかしていた。どうやらレモンザメという名のサメがいるらしい。その水槽には飼育員が清掃に入る度にいたずらをするとの理由で、巨大水槽からこちらへ移されたエイの一種もいて、やや同情をさそわれた。私も小学生時代は落ち着きのなさから、よく教卓脇に机を移動されていたのである。しかし、私はこれを懲らしめだとは思えずに、額面通りに「特等席」であると思っていたものだ。これは今でも私にとっては自慢話の類である。あくまでも私にとって、ではあるが。
ジュゴンが水面に上がって空気を吸い込み、その尾びれをばったりと一振りして水槽の底に沈んでゆくのを見た。
水底では生物というよりもなにか一つの塊が沈んでいるかのようである。息をするのも、尾びれを使うのも簡潔でゆったりとした静かさである。静かな塊。
備瀬最後の夜にペンション裏手の浜に出た。
新月で月のない中、天の川が見える。もうすこし寒くなると、こうした晩には手長ダコが磯に上がってくるのだそうだ。
夜空の写真を撮影しているというボビー氏に言わせると、向こう岸かと思っていたものは台風の影響で現れた雲の塊とのことだった。ああした雲があるときには、頭頂に星々をいただきながら稲光の走るのをみることがあるのだそうだ。
私も夜の引き潮に取り残された生物を見ようと歩けば、イワシの子であろうか。光に集まっては私の動くのに心を驚かせては小魚が散ってゆく。取り残していった引き潮を居ながら追うようにしてナマコが岩のはざまにぐったりとしている。
ふと砂浜のほうを振り返ると先ほどまで点灯していたゆっぴの懐中電灯が見当たらない。星でも眺めているのだろう。そう思いつつ砂浜のほうへ戻ると、二三の座る人影が見えた。近寄ろうと歩みを進めると、その人影とは離れたところ、うっすらと星に反射した砂地の中に何か黒いものがあるのがかすかに分かった。先ほどは気が付かなかったが何かが打ち上げられているのだろうか。近づき電灯を当てると、その黒いものは星を見ているうちに眠り入ったゆっぴであった。見れば懐中電灯もサンダルも飲みさしのチューハイもそこいらに投げ出された状態である。Sinbowさんが言っていた。「砂浜で星を見ながら寝るのはほんとに気持ちがいい」。確かに気持ちよさそうである。しかし初日にPoさんが虫にかじられたのも浜であったようだし、なにより明日は朝から移動だ。そのままにしてもいいのかもしれないが、やはりそのままにしても帰られないと思い、一応声をかけることにした。声はかけたが反応がない。ぷっす~とかいったような寝息を吐いたりもする。人が気持ちよく寝入っている状態というのはどこかふてぶてしさもあるものだ。あるいはそれは人が意識を離れて自然と言うものを体現している状態なのかもしれない。かるく頬をたたいてみた。ぴたぴたと音がしただけで、名を呼んでも返事がない。プロデューサーがその師弟愛ゆえ、愛らしさを譬えた一語「ジュゴン」というのが思い返される。その言葉とあの美ら海水族館で見た水底に息をひそめた一塊の影とががごく自然に重なってくるように思われる。寝入ってなにか物質的になってしまった人というのは、それゆえにとでもいうべきか、なんだか静かなものである。備瀬の環境は、人の自然であるとかあるいは野生を引き出す働きがあるらしい。
やや心配にもなったので、もう少し強く頬をうって目を覚まさせた。「えっ?うそ、なんでここにいるの?!」と一言言い残し、むっくり起き上がって帰ろうとするところへ、並んだ影法師のあたりから「アツアツのカップルのところに、僕一人置いてけぼりにする気?」と聞き覚えのある声がした。その声を聴いたゆっぴは、踏みとどまって海へと一度向かったのだが、やはり眠たさが勝ったらしい。それから急にUターンしてペンションへ続く道の方にと走り出した。懐中電灯もつけずにである。しかし星明りだけでは道を照らすに不十分であった。ザザッと踏みとどまった音がして懐中電灯が灯る。岩と木々に行く手を阻まれたのである。そして、宿へと通じた細道を見出すと、またも猪突猛進。足場は決していいとは言えない。ヤシガニやヤドカリが潜む道である。大丈夫であろうかと、ちょっと心配にもなり追いかけていくと、その細道の出口近くで「え?誰?レモンさん?」と、今度は誰かに追っかけられたことにと不安を覚えたらしかった。
こうした一連の動きを物珍しく見た。宿の玄関にたどり着くと、電灯に照らし出された彼女の腕から背中にかけては罌粟の実に覆われたアンパンのようであった。それにしても罌粟の実をまぶしすぎだ。
「ねぇ、砂払って!」と言われたが、ここで甘やかしてはいけないなと思い、ほかの人に迷惑のかからないよう自分でなんとか始末してくれるようにと、あえて砂を払うことはせず、やや冷ややかに対応させてもらうことにした。
沖縄にもジュゴンが生息しているとのことだが、私が今回生体で見ることのできたのは美ら海水族館でのアメリカ大陸出身のものと、この夜に浜で驚かされた似てまた非なるなにかしらくらいのものであった。いずれはあまもをはむ姿を沖縄で見ることができるであろうか。あることを願いたい。
しかし、こうしてクリエイションに関して思い出すことを話しているのだが、今のところ私としてはこうした出来事の何が重要であって、何が略されるべきことなのか、どうも判断ができずにいる。思い出されることは面倒に思わない限りは記してみようとは思っているのだが、時折思い出しはしたものの、そのことに触れるにはなにか時宜を得ないように思われて億劫になったまま保留にしてしまうものもあるだろう。それでも何かしらの話に連なってよみがえってきた記憶に関しては、もしかするといずれなにがしかの考察につながるかもしれないために話しておきたくもある。いや、面白がった記憶は構えて考察なんぞといった言い訳をしつらえずとも、状況性を伝える方便ともなれば、なにかしらの問題意識と自然につながっていたりもするようにも思われる。
それにしても、時間の共有されていた時には親しみを込めて用いられた形容も、時間を経て文字化されるとどうしてもその語彙が使われるに至った雰囲気の全体には欠け、その客体化された語句の意味合いをいかようにも読み替えられることに気が付く。プロデューサーの師弟愛の表れでもあった「ジュゴン」のたとえは、備瀬でのクリエイション中、ゆっぴにPoさんとのデュオシーンに振り回し型のリフトが挿入されていることと共にあった。そのため、リフトのあるシーンを行うたびに「あぁ、どうしようあたしもう少し痩せとけばよかった」とかなんとかゆっぴはもらすのだが、しかし次の瞬間には昼食や夕食のことを考えていたりもする。それも彼女なりに長期にわたる滞在制作の中で大事な事務連絡を共有必要性をおぼえての、気を利かせてくれた結果でもあっただろう。いや、ほとんどの場合は彼女自身の主要関心事ではあったようだが。もしかすると、リフトがあるシーンの必然性を解釈しきれずにいることへのささやかな抵抗もあったのかもしれない。
クリエイション・ドキュメントというのは改めて難しい。どこまで語ることでそのクリエイションの性格を示すことになるのか。できることなら、その中で体験したことと思索したことのすべてを、参加者全員がそのすれ違いも含めて多角的に提示し、その中で何をシーンに採用し、なにを不採用にしたのかを明らかにできるなら我々の作業を一つの事例としてその先の創作へのたたき台に資することができるようになるのかもしれない。いやそれだけなら、もっと簡潔に作品作りに関することのみを記せばこと足りるかもしれない。今回のクリエイションは、確かに作品作りを目的の一つにはしているが、それ以前にいかに異なる文化背景の者が集って一つの作業を遂行できるか、という点により重点が置かれていたはずである。その作業、そしてそれと不可分にあるコミュニケーションについていかに記すことができるか、ということがおそらくは今回の主要事項となるはずではないか。さて、改めて何を記したらよいだろう。その判断がなかなかつかないので、この遠回りをはさんで、やはり思い起こされることで口をついて出てくるものだけをとりあえず記して置くよりほかなさそうである。
うまい事行けば、それは我々のコミュニケーションとともに築きあげられた信頼感のようなものをも表すことにとなるのかもしれない。あるいは、私のサービスによってそういったことなどを過剰に演出もしてしまうかもしれない。まぁ、とまれもうまれ、話し及んだジュゴンにまつわるエピソードは思い出された事柄の一つである。この辺りはいずれゆっぴがその雰囲気について投稿してくれることで一応の相対化、もしくは温度差が露わになることを願うところでもある。そう、コミュニケーションというのは複方向に行われて成立するわけだが、しかしその複方向には、必ずしも個々の方向性にかかる力が均質であるとも限らないのである。いやそもそも成立しているのかすらわからないような関係性と言うのもにと、我々は晒され続けてもいるのではないか。あぁ、実は今少し頭がくらくらしているために、話がどっか遠いところへ飛んでいきやすい。解決しえないことを抱えたまま、私たちは人に出会い、解決しえないことを抱えたまま、ほんの小さな共通項を見いだせたことに一喜一憂しながら手を取り合い、時にその共有に抱擁するのだ。
とりも直さず、ゆっぴは自身の感覚に忠実な天真爛漫さを湛えた、健康的な一人である。その明るさゆえに、皆一様に親しみを込めて彼女とクリエイションを共にできたのは事実である。
水野さんからの師弟愛を皆に垣間見せつつ、彼女は彼女のクリエイションにおける立ち位置を模索していた。備瀬でのクリエイションにおいては、おそらくもっとも忙しく働いたうちの一人であった事だろう。いや、それぞれがそれぞれに働きを見せていたはずである。その中で、考えを示す一人のメンバーのみならず、私と香港チームをつなぐ位置にも彼女はいたのである。事前段階で、このことに大いに不安を抱えていたということを彼女は後々語ってくれた。しかし、面白いもので、川口さんの通訳とは異なった次元で、彼女の通訳は働きを示し、そのことが相乗的に新たなコミュニケーションを際立たせたことろもあるように思われるから、こうしたクリエイションと言うのは面白い。
備瀬を立つ朝、昨晩は砂の罌粟粒をたっぷりまぶしてアンパンみたいだった旨伝えると、彼女は「ごめーん」と言いながら、ひざから頽れるようにして笑っていた。
remon